喪
どうもこんにちは。
あまたの植物を自前のデス・ハンドであの世送りにしたあまぼしすずめ(@S_amaboshi)です。
先月エ・ダ・マメコさん(享年70日)を逝去させてしまい、喪に服しておりました。

四十九日の法要も終わったので、どうして枯らしてしまったのか原因を考えてみようと思います。
枝豆は素人でもカンタン!
との謳い文句で始めましたが、世の中の【カンタン】【普通】が自分に通用したことがあったでしょうか?
植物どころか、自分のお世話もできない人間です。
- 種を撒きます
- 芽が出ます
- 水をあげます
- そして収穫
- ね? 簡単でしょ?
みたいな感じでいうの、本当にやめていただきたい。
「家庭菜園はカンタン」という言葉は、運動部の「10キロ走るなんて余裕」くらいの信頼度だと心に留めて生きていこうと決めました。
とはいえ、植物を毎度枯らしてしまう人は私以外にもいるはず。
そういう人は、やはり何かしらマズいことをしているのだと思うんですよ。
……で、今回は枝豆栽培を振り返り、次に生かせるよう備忘録としてまとめました。
同じように「枝豆枯らしたわ……」という方は、一緒に振り返ってみましょう。
それではLet’s reflect!
Contents
枝豆栽培をするうえで押さえる6つポイント

そもそも枝豆を育てるためには、何が必要なのでしょうか?
簡単にまとめました。
枝豆は日当たりを好み、適温は20~25℃
枝豆は陽性植物※であり、日当たりが大好きです。陽キャ!
直射日光が当たっても問題がないため、日照時間が長い東~南での栽培がベストです。
※ 耐陰性が弱く、日光が十分に当たる場所で生育する植物
種まきは4月中旬~6月上旬
種類や地域もよりますが、種まきはだいたい4月~6月。
早すぎると寒さにやられてしまいますし、遅すぎると発芽のころに気温が高くなり蒸されてしまうのだとか。
移植を嫌うので種からがおすすめ
枝豆は移植――つまりは植え替えを嫌います。
出来れば生まれた時から同じ環境に居たい、というわけです。
意外に保守派ですね。
直播(直接地面に蒔くこと)が良いですが、鳥が好むため、直播をするときは防鳥をしなくてはいけません。
ポットから移植する場合は種を撒いてから約20日ほど経ち、本葉が1.5~2枚程度あるときがベストです。
プランターは60センチほどの大きめ推奨
プランター栽培をする場合は、深さ15~25センチくらいは必要です。
幅は60センチ×35センチほどあれば安心。
60×15ほどのサイズで挑戦している方もいて、真似をしましたが駄目でした(後述)。
乾燥に弱いので水はたっぷり
枝豆は根が短く、土の水分を吸い上げることが苦手です。
つまり乾燥に弱いので、水やりは忘れないように。
一度にたっぷりあげましょう。
肥料は少なくてもよい
マメ科の植物は根に根粒菌(こんりゅうきん)と呼ばれる微生物が共存しており、自ら窒素肥料を作る性質があります。
土づくりをちゃんとしていれば追肥はいりません。
プランター栽培は野菜の土を利用すればOK。
しかし葉が黄色っぽくなってきたら肥料切れの状態なので要注意です。

- 日当たりを好むので、適温は20~25℃
- 種まきは4月中旬~6月上旬
- 種から同じ場所で育てる
- プランターは60センチほどの大きめ
- 乾燥に弱いので水はたっぷり
- 肥料は少なくてもよい
そんなわけで私は、育てる前に上記6つのことを知識として頭に入れて置きました。
わかっていたつもりだったのですが、結果どうなったのでしょうか……?
枝豆を枯らしてしまった原因7選

「良くなかったんだろうな~」という原因を7つ挙げます。
思い当たる節が多すぎてどれが原因だったのかわからないので、とりあえず全部書きました。
初心者向きの種類を選ばなかった
枝豆は極早生(ごくわせ)・早生・中生(なかて)・晩生(おくて)と、栽培期間により種類が異なります。
初心者には、早生~中生がおすすめ。
さっさと作ってさっさと収穫しろということです。
しかし私が選んでしまったのは――黒豆
なんかイイじゃん、黒豆!
出来たら納豆作ろ!
くらいのノリでしたが黒豆は晩生種が多く、私の選んだ種も例外ではありませんでした。
どうしていきなり蔵人感あるチョイスしちゃうの……?
種まきのタイミングが遅かった?
タイミングが遅かったというより、運が悪かったとも言うのかもしれません。
6月6日に種を撒き、5日もすると発芽しました。

……が、ここで梅雨入りになってしまったのです。
しかも今年は長梅雨で、毎日がお手本のようなしっかりとした雨模様。
結果として、日がほとんど当たらない幼少期を過ごすことになります。
もうこれは不良コースですよ……。
プランターで育てるのに移植した
プランターで育てるのに、なぜかポットに植えました。
そのため移植する必要がでてきたのです。
できるだけ傷つかないようにはしましたが、いつまでも本葉が開かなかったため移植の時期が遅かったようにも思います。
水やりのタイミングがわからない
乾いていたらたっぷり水を以下略、みたいな曖昧な指標がそもそも苦手でして……。
土を触って水気はないような気がするし、でもカラカラというわけでもない。
あげていいの? 今日はあげなくていいの?
水やりの判断がまるで出来ないんですね。
臨機応変という単語は前世に置いてきたので、社会に出て一番使えないパターンです。
社会に出ていないことが唯一の救い。
家庭菜園うんぬんではないところにも落とし穴がありました。
あとジョウロを持っていなかったので、ラウンドアップのケースを丁寧に洗って再利用。

成分は残っていませんが、絵面がサイコパスのそれ。
出が悪いため水やりにイライラしましたし、そもそも1回の水やりが少なかった可能性が大いにあります。水不足ですな。
日照時間少なすぎ問題
おそらく8割の原因。
私が育てていた場所はベランダなのですが、ウチのベランダは西向きです。
しかもコンクリート造りで、スキマから日は差さない。
風通しも最悪。
さらに隣家とウチの屋根で陽光が遮られ、日照時間が正味3時間くらいしかありません。
正午近くになりようやく日が差します。

たったこれだけ。エグイ。
高さを調節するなどして日を当ててあげればよかったのですが、とくに対策をするわけでもなく放置。
結果として徒長が止まらず、風が吹いても倒れそうな状態で、いつしか葉もつかなくなりました……南無。
プランターが狭すぎる
「幅15センチくらいでもいける!」との情報を見て、15×60くらいのサイズで始めましたが……どうも小さかった模様。
苗と苗の間は30センチくらいあけましょう!
みたいな意見もあり、何を信じていいのか分からない。
敗因はむしろ情報社会にあったって感じ。
虫に食われた
マイマイガとかいう、およそ人類になにひとつの恩恵ももたらさないであろう害虫がいるんですけれど。

こいつが時々大量発生するんですね。
長野県内のいたる市町村で注意喚起がされていました。
我が城の壁に卵が50個くらいあって、どうにも出来ないので来年を憂いています。
ベランダだから大丈夫だろ、と慢心していたところ、この幼虫に葉のほとんどが食べ散らかされてしましました。

毛虫が湧いてしまったら遅いのですが、予防としては木酢液を使うのが良いとのこと。
木酢液とは、木を焼いた時の水蒸気を冷やして液体にしたものです。
水で稀釈して使うと、植物には無害で害虫予防になります。
園芸って手間ヒマ掛かりますねえ……。
まとめ なぜ育つと思ったのか?
以上、枝豆栽培が失敗したと考えられる要因でした。
むしろ、なぜこの状態で植物が育つと思ったのだろうか?
なかでも大事だと思ったのはやはり、
- 水やり
- 日照時間
- 害虫対策
の3つですね。
次回はここら辺を注意しながら家庭菜園を行ないたいと思います。
まずはジョウロの購入でしょうか。
家庭菜園で失敗してしまう人は、このように原因を細分化して考えてみてください。
後日談
故エ・ダ・マメコがいた土地に、無料で配布されていたラディッシュを植えてみました。
別名『はつか大根』
「子どもでも育てられる」というほど、初心者向けの野菜です。

……そろそろ一か月が経ちますが、どう見てもコレジャナイ感がぬぐえない。
子ども以下か?
いっそ水耕栽培でも行ってみようかなぁ、なんて思いますが……まあ、水を腐らせるんでしょうね。
――私の戦いは続く。
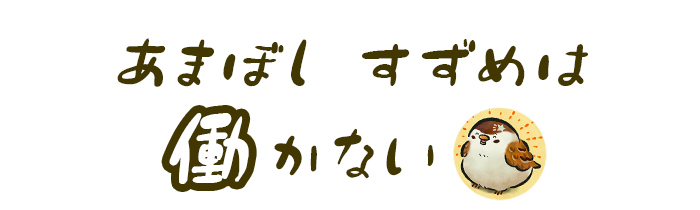







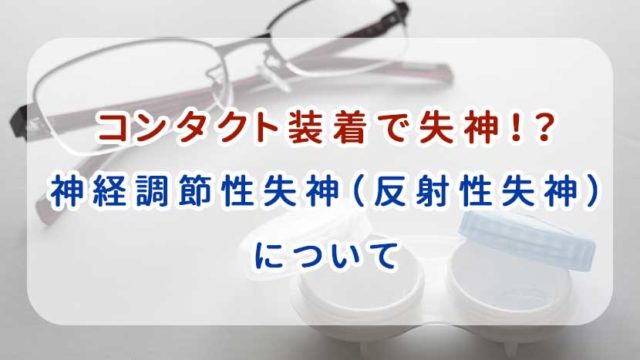


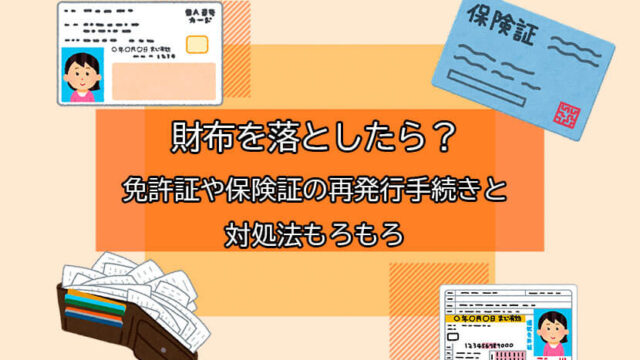



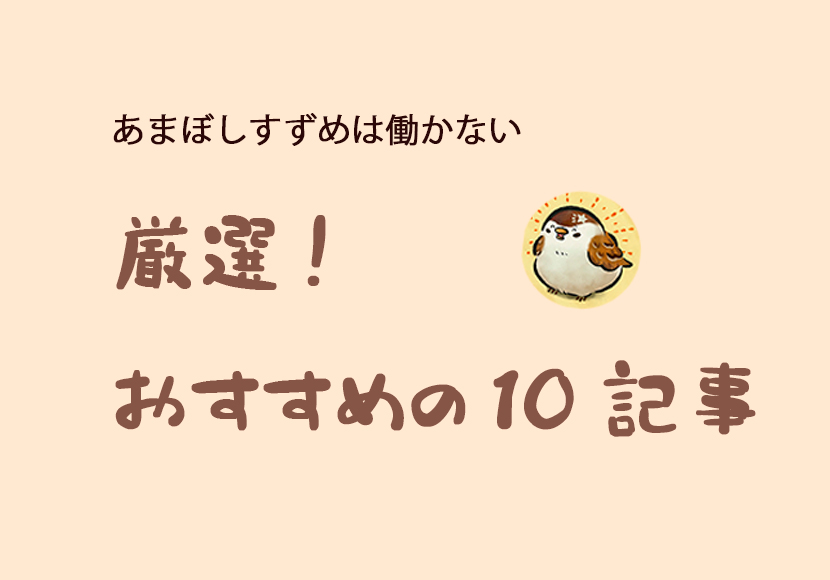




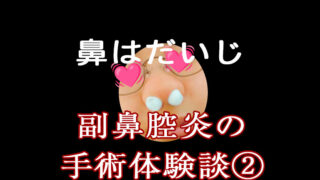





私も枝豆駄目にしそうです。
ガレージで育てているので日照条件が悪すぎますね。
苗を買うのは好きなのですが、まともに育ったのは少ないです。特にハーブ類。あれこれ買ってみんな駄目になりました。
今年こそは頑張ろうと思っていた矢先なのですが。うちのエ・ダ・マメオさん、もう少し生き延びて‼️
>ランランさん
コメントありがとうございます。
簡単!と言われている家庭菜園は日照条件がよいことが前提なんでしょうね……
意外と難しいと思い知らされます
エ・ダ・マメオさん頑張ってくださいっ!!