どうもこんにちは。
本の虫……と見せかけたただの虫・あまぼしすずめ(@S_amaboshi)です。
以前「10冊の読書術本から選ぶ最強の3冊」で、読書術の本をご紹介しました。
3冊の本について個々の感想はいずれ書くとして、今回は色々な読書術の本を読んで学んだ読書のコツについてまとめます。
多くの読書術本に共通して書かれていたことです。
本当はこれらの本を実際に読んでみるのが一番なのですが……。
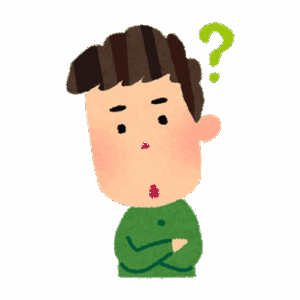
読書術ってどんなものなの?
という方のために、概要を紹介します。
この記事を読んで「もっと深く知りたい!」と思った方は、ぜひご自分で読書術の本を読んでみてください!
上記の方は、これから紹介する内容を少しずつでも実行してみましょう。
読書に対する考えが変わるはずです……!
(※ 紹介するのは実用書を読む方法であり、小説など文学作品はあてはまりません)
読書をする上で大切な5つのポイント
早速ですが、読書をする上で重要となる5つのポイントはこちら。
- 読書の習慣を身に着ける
- 能動的に本を読む
- 本文以外のところから読む
- 読書に緩急をつける
- ジャンル読みをしていく
具体的にどういうことでしょうか?
読書の習慣を身に着ける
なによりもまず読書の習慣を身につけること。
「時間が空いたら読書をしよう」と思っていると、なかなか読書をすることができません。
1日15分でもスキマ時間で読書をする

いや、だから時間がないんだって……!
と思う方もいるかもしれませんが、まずは1日15分、読書に当てられる時間がないか考えてみてください。
通勤中の電車、風呂、朝起きてからor寝る前にスマホをいじっている時間……。
15分なら見つけられないでしょうか?
場所はどこでもかまいません。
できるだけ固定の読書時間をつくるところがポイントです。
逆にどう頑張っても15分の時間も見つけられないくらいギチギチに忙しい人は、ヤバいです。
読書術の前に考えなくてはいけないことがあるかもしれません……。
スキマ時間で本を読む、という点ではAmazonのキンドルがおススメ。
端末を買うのはちょっと……という人は、スマホアプリがあるので、それで試すのもアリだと思います。
制限時間を設ける
固定の読書時間が見つかったら、
といったような制限時間を設けることで、読むスピードを上げることができます。納期や締め切りがある仕事の方が早く片付くのと同じですね。
とはいえ、
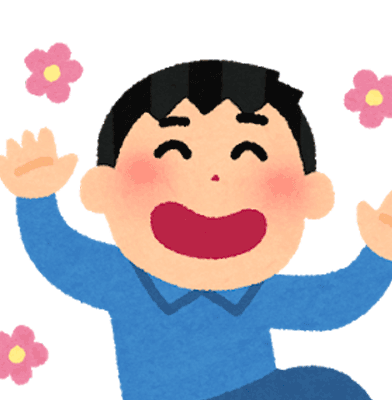
5分で1冊読むぜ~
といった不可能な目標設定ではなく、2時間で1冊くらいの現実的な目安を本の内容や量によって決めるのがよいでしょう。
1日15分でも読書を習慣にしよう
読書には制限時間を設けよう
- 1日15分でも読書を習慣にしよう
- 読書には制限時間を設けよう
読書は能動的にする
ただ文字を追うだけだと、なかなか記憶に残りません。
能動的な読書ができる4つのポイントがあるので、意識してみてください。
- 読む本は、自分がいま必要としている知識が書かれた本
- この本から何を学びたいのか、目的意識を持つ
- 読みながらアクションを起こす
- 読書後はアウトプットをする
本の選び方 自分にとって為になる本とは?
読む本は「みんなが薦めている名著だから」という風な理由ではなく、自分が今、知りたいと思っていることが書かれた本を選びましょう。
明日の自分のためになる本です。
資格の本やダイエットの仕方、絵の描き方、英語の参考書……。
なんでもよいですが、自分が身に着けたいものが書かれている本こそが、自分にとって一番ためになる本です。
読書の前に目的意識を持つ
目的意識などというと意識高い系ですが、まあ意識高く読んでみましょう。
簡単にいうと、
ということを考えてみるということです。

この本から正しいキノコ栽培の知識を得るぞ!

この参考書で簿記に受かるんや!
みたいな感じでOKです。
それが本を読む意欲になり、内容を吸収する力を上げてくれます。
できれば付箋に書いて本の最初に貼っておけば、飽きてきたときに見返すことでモチベーション維持につながるでしょう。
読みながらアクションを起こす
本を読みながらマーカーを引いたり折り曲げたり、コメントを書いたりと、本を汚して読んでいく方法がおススメです。

コメント……?
難しそう
と思う方は、「面白い!」「へえ、知らなかった!」と思ったところに、そのまま『面白い!』『意外! 初耳!』といったリアクションを書くだけでも効果があります。
なぜなら人は感情が動いたことの方が記憶にとどめておけるからです。
実際の生活の中でも、日常よりも悲しみや嬉びが強かったエピソードを覚えていると思います。
そのような感情を利用することで、忘れにくい読書をすることができるのです。
ノートやマインドマップでまとめる方法もアリですが、その際には丁寧さよりも視覚的なわかりやすさを優先してみましょう。
読書後はアウトプットをする
本は読んだあとが大切で、読みっぱなしはいけません。
アウトプットをすることで記憶に定着するので、小さなことでもなにか行ってみましょう。
など。
今私がやっているのもアウトプットになります。
学生時代、人に勉強を教えたら自分も理解が深まった、という経験がある人もいるかもしれません。
同じような感じです。
他者がいなければ、自分に説明するように1人教師ごっこをするのもおススメです。
……端から見たら不審者。
いずれにせよ、大切なのは読みっぱなしにしないこと。
マインドマップを用いたアウトプット方というのもありますので、興味がある方は活用してみてください。
- 読む本は、自分がいま必要としている知識が書かれた本
- この本から何を学びたいのか、目的意識を持つ
- 読みながらアクションを起こす
- 読書後はアウトプットをする
本文以外のところから読みはじめる
3つ目のポイントは、本を最初から読まないということ。
あたりまえの感覚で、本は1ページ目から読みだす人がほとんどだと思いますが、実はそうでなくても構いません。
というかそうしない方がいいかもしれません。
本はまず、
といった本文以外のところに目を向けてみましょう。
すると、「この本は○○についての本」「作者はこういう話をしたいのかな?」というのが見えてきます。
また実用書の目次は小説と異なり、ネタバレ感がすごいです。
ここをよく読んで、

この章は××についての話だろうな

○○の3つの法則って何だろう?
と知らないことと、すでに知っている知識を分けたりします。
その際とても面白そうな項目があったら、そこだけ読んでしまっても大丈夫です。
物語ではないので、本の真ん中から読もうが問題ないのです。
- まえがき・目次・あとがきから読んでみよう
- 途中のページでも気になるところから読みだしてOK
緩急をつけ本当に重要なことを読み取る
多読の正しい方法について。
速読と呼ばれる、メチャクチャ速く読書をする方法が一時期流行りました。
しかし現在では、速読はほとんど意味がないという意見が大多数になっています。
1冊5分で読むとか、当たり前ですが内容が頭に入るわけがないのです。
私も浪人時代、頭が狂って『1分間ひたすら参考書を捲り続ける勉強法』みたいな本に手をだしましたが、結果はお察しの通り。
現在は速読より、多読(精読)と言われています。
これは重要なところは丁寧に読み、それ以外のところはサッと読み飛ばすという読み方。
つまり緩急をつけた読書方法です。
すでに知っている知識が書かれたページは速く読めるので、知っていることが多くなればなるほど、読み飛ばすページが増えます。
つまり知識が増えれば増えるほど、本を読むスピードが速くなるということ。
めちゃくちゃ頭がいい人や本をたくさん読む人の読書スピードが速いのは、そもそも書かれていることが既知になっている知識量が土台にあるから、というカラクリですね。
本当に重要なのは2割程度
本の隅から隅まで、すべてを覚える必要はありません。
というか多分できないです。
だいたいの本は、本当に重要なこと・主張は2割程度と言われています。
その2割のうち、8割方を理解して覚えることを目標に読書をしてみるのがおすすめです。
全部を覚えなくていい、と思うだけで気が楽になりますね。
完璧主義な人ほど最初からしっかり読みますが、わからない箇所で挫折してしまったりもします。
しかし、あまりに理解不能なところは飛ばす、くらいの心持ちでOK。
まずは通して読んでみましょう。
難しい箇所が理解できずとも、2割ほど必要な知識が身に着いたのなら合格点です。
もっと知識をつけて、また読み直せばいいのです。
読書はジャンル読みがよい
最後は本の選び方。
気になること・知りたいことがあるなら、そのジャンルの本をまとめて一気に読むのが効果的です。
具体的には5冊~10冊、さらに知りたければ20冊ほど。
これくらい読むと、そのジャンルについての知識がかなり深まります。
同じようなことが毎回書かれていると思うこともあるかもしれませんが、それこそがそのジャンルにおいて重要なポイントになります。
逆に異なる意見が出てきた場合は、自分なりにどちらを信じるか・実践するか答えを出してみてください。
同じ作者の本を芋づる方式で読んでいくのもおススメ。
ただし同じ人の本ばかり読むとその人の思想に傾倒してしまうこともあるので、一定量読んだら別の人の本にも手を出してみましょう。
- 本はジャンル読みをしよう
まとめ
以上が正しい読書の方法でした。
振り返るとこのポイントはこの5つです。
- 読書の習慣を身に着ける
まずは1日15分の隙間時間
制限時間を設ける - 能動的に本を読む
自分が必要としていることが書かれた本を選ぶ
目的意識を持つ
読みながらアクションを
読んだらアウトプット - 本文以外のところを見る
まえがきや目次、あとがきから読んでみる
本の好きなページから読んでOK - 読書に緩急をつける
大事だと思った点は丁寧に、それ以外はさっと読む
本からの2割程度の知識を得る - ジャンル読みをしていく
気になるジャンルの本は一気に10冊ほど読んでみる
たくさんあって面倒……と思うかもしれませんが、出来そうなところから始めてみてください。
数冊読む頃には慣れてくるはずです。
読書術の本に共通して書いてあることをまとめましたが、作者によっての違いもあります。
より詳しく読書のやり方について知りたい人は、ぜひ一度読書術の本を手に取ってみてください。
【おすすめの読書術本はコチラ】
それでは良き読書ライフを!!

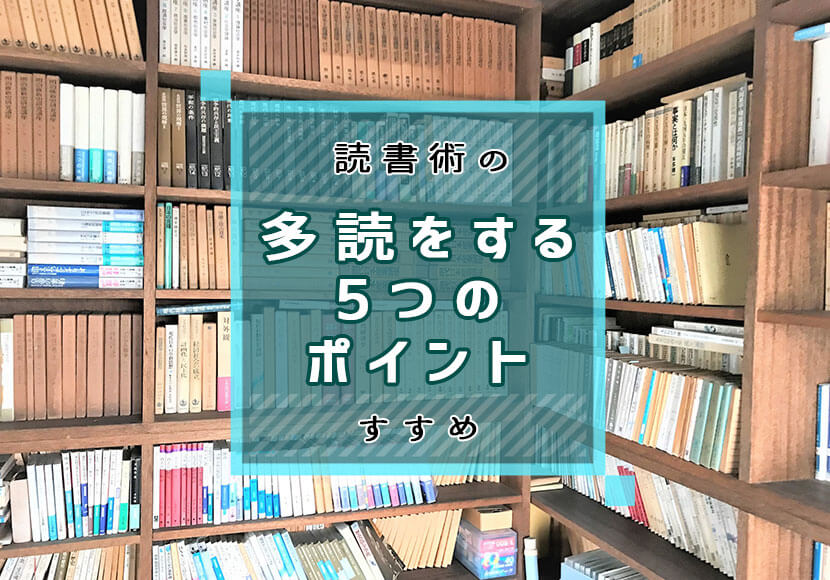
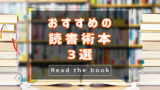
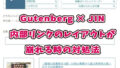

コメント
参考になりました。
「現在は速読より、多読(精読)と言われています。」を読んで、やっぱりな、と思いました。
速読したいけれど、できない自分に、どうしたらよいか読書方法を探していました。
速読できない原因として、自分には基礎知識が不足していることに気づかせてくれました。
まずは精読して基礎知識を増やしていこうと思います。
ありがとうございます。
>ゆうやさん
コメントありがとうございました。
昔は1冊数分で読める、みたいな速読法を信じてできない…と思っていましたが、今はそういう方法は否定されているみたいですね
地道に精読+多読がいちばん速読に繋がりそうです。おたがいがんばりましょう!